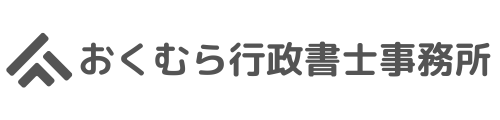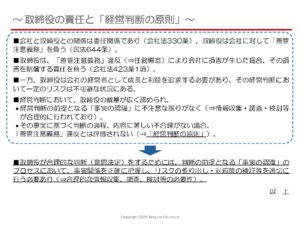AIの活用
2025年2月6日付の日本経済新聞(朝刊)で、子どもの読書教育アプリを手がける会社が、AIが子どもに読書感想文の書き方を指導する新機能を投入したという記事を目にしました。
投入された新機能は、利用者はAIとの会話の中で「ヒント(箇条書き)」をもらい、これを参考に利用者自身で感想文を書き上げることで表現力の向上に繋げる、というものだそうです。
私が共感したのは、その「着眼点」。AIが自分の代わりに感想文を作ってくれるとか、上手な文章に整えてくれる、というような「考えるプロセスを代行する」ことが目的ではなく、あくまで「能力向上」が目的であるという点です。
私自身、ひとりで仕事をしていることもあり、作業の効率化や省力化のためにAIを活用しています。AIを活用することで、単純ミスの発生防止に繋がったり、課題解決のヒントをもらうこともあります。時代が進むにつれ、新しいツールが沢山開発されるはずですので、今後も積極的に活用したいと思っています。
ただ、大切なのは自分の「存在価値」。必要とされる存在であるために、スキルアップを続けていかなければと感じます。逆説的ですが、自分の「存在価値」を高めるために、AIを「積極活用」していきたいと思います。
※生成AI活用時、機密情報や個人情報は除外しています。